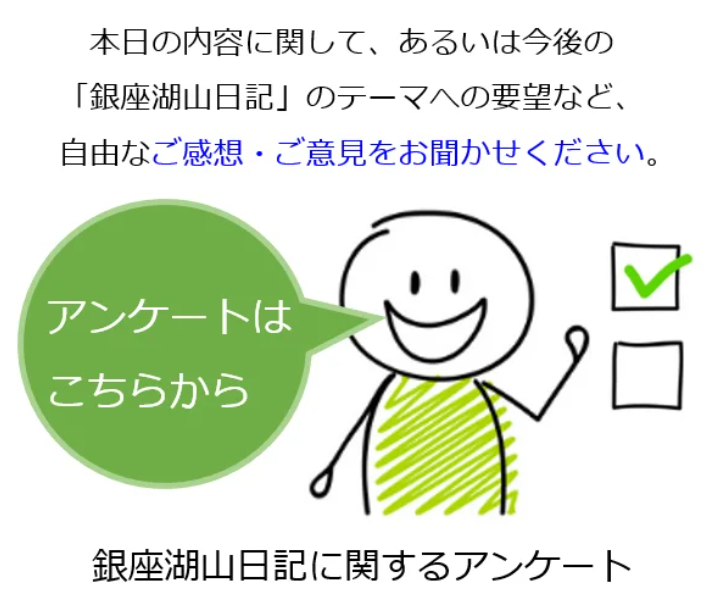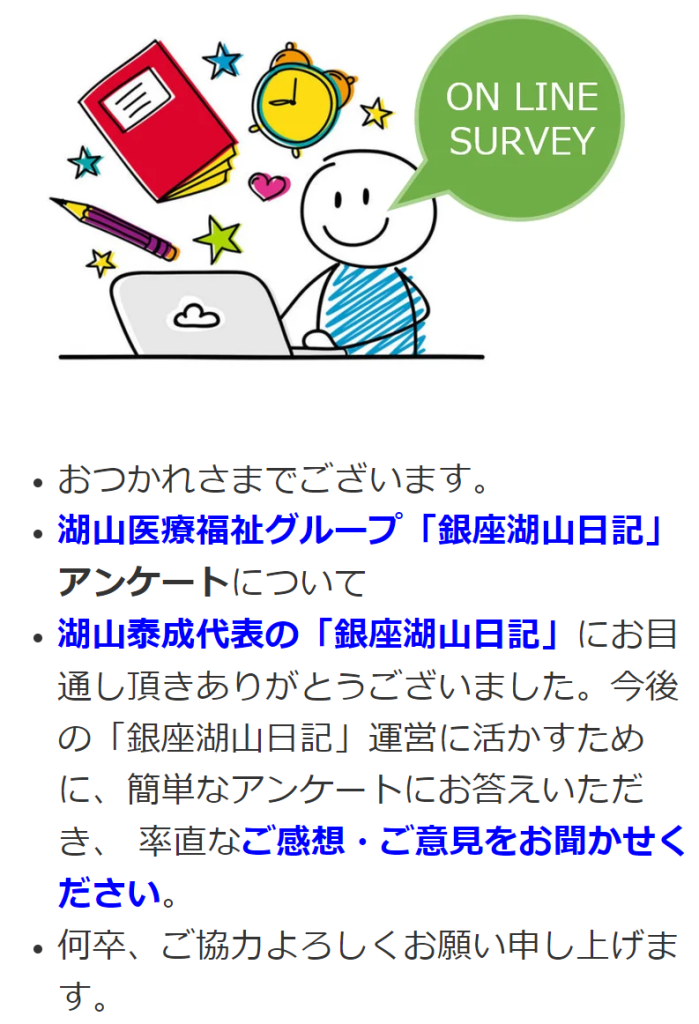日本工芸と現代美術

私は、コロナ迄は、東京の主だった美術館を毎月、殆ど廻っていた。
周っていた、と言うのは、その日一日かけてその地区の美術館を観て回る。
上野だけで、6つの美術館、博物館がある。
早足でも、休む時間もない。
美術館トライアスロンである。
まずは、何をやっているか現地調査。
六本木、銀座、渋谷、新宿、京橋、汐留と都心なので、半日で行く所もある。
美術館散歩、ワンダーフォーゲル、ハイキング。
展示開催初日に招待される事もあるが、その日は、招待者の頭越しに、行ったり来たり。
気に入った展示は、何度でも、観に行く。
30分でもあれば、入場する。
映画鑑賞と同じ。
きっと、映画館と同じ、美術館と言う環境が好きなのだろう。
でも、レストランは殆ど使わない。
女性客で占められていて、騒がしく、私の行く所ではない。
お勧めは、美術館の中の図書館。
そこには、高価な美術の希少な本が揃っている。
一日中いても、飽きない。
でも、コロナでぱったり、行かなくなってしまった。
入場予約が嫌いなのである。
その時の気分で、飛び込む。
ハシゴもする。
飲み屋ではないが。
心が欲している時に、求めているときに行く。
自宅や、職場の身近に置いてあるアートとは違う。
遠くに旅する気分なのだと思う。
芸術を求める心の旅。
異国への放浪の旅。
己とは違う価値観、普段とは違う世界、異境へのフライト。
現代美術が好きだったのだが、最近は、陶芸や漆器などの日本工芸に関心を強く持つようになった。
美術館に飾るよりも、普段の生活の中で生きた形で残せないか。
保存ではなく、未来への進化として。
子供の時から、普段使いをしないと、関心も、審美眼も育たないのではないか。
また、産業としても生き残らないと、製造が維持されない。
天才作家1人では、生まれ得ない。
多数の利用者と、製造業者がいないと維持できない。
工芸は、産業でもあり、国民生活文化そのものである。
金持ち老人の趣味ではない。
懐古趣味でもない。
現代美術の創生は、長い伝統工芸の歴史文化の基礎の上に花咲く。
そう、考えるようになった。
工芸技術があって、世界に通用する新しい美が生まれる。
でも、朝の歯磨きのうがいのコップは、銀行記念品のプラスチック。
普段使いの食器、コップも頑丈な物ばかりだ。
朝食は、キッチンで、立ったまま、テレビニュースを見ながら食べる。
テーブルに座って、ゆっくりと食する生活習慣を取り戻すのが先。
私自身の生活を見直す事が、優先なのは、間違いない。
パルスオキシメーター 96・98・97
体温36.3 血糖196
館長 代表 湖山泰成